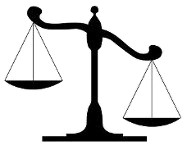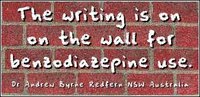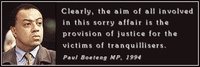裁きは公正ですか?

注 記
- このセクションでは、私が闘った日本の裁判についてお話します。特にそこで現れた、明らかに不当な処置と思われる事例のかずかずを紹介します。これらの事例をわかりやすくお伝えするために、「東京高等裁判所の判決」と「中毒治療科の報告書」への参照箇所(リンク)がいくつか出てくるので是非ご参考ください。また、「中毒治療科報告書」は、一貫して、法的証拠およびDSM-IV-TRの依存症診断基準に基づいて書かれていることにもご留意ください。
- 裁判官の「信頼性のある証拠に基づいた主張しか認めない」という指示に従って、私が裁判所に提出した資料は全て証拠に基づいたものばかりです。もちろん、当サイトで示した資料についても言えることです(私の主張には、どの段階においても、証拠のないものは一切含まれていません)。
- 証拠(カルテ)に関連する報告書の内容の一貫性と信頼性についての記述は中毒治療科第3報告書の3.4項目をご覧ください。
- 診断基準不採用:判決書では、3つの基準が無視され、その結果、私がDSM-IV-TR の診断基準に適合する薬物依存であったという事実を除外していない。このDSM-IV-TR基準が、本訴訟全体の基礎になっていた。
- 証拠を間違えて引用:高等裁判所の判決は「各添付文書には大量連用により薬物依存が生ずる可能性があることの記載があるのみであり」ということになりましたが、「大量投与又は連用中」という記載もありました。
- 臨床的関連情報不採用:例、以前は神経性疾患、精神性疾患などの病歴は一切なかった事実、断薬と減薬を試みるが何度も失敗した事実、薬剤治療開始前には、まだ就労能力があったが、薬剤治療を受けてからは就労能力を失い、また離脱治療後には、再び就労能力を取り戻した事実など。
- 選択的症状分析:裁判は私が依存状態にあったか否かという判断については、全体を見ようとせずに、大幅に省略し抜き出された特定の一部分だけの症状を基づいた。
- 離脱症状不採用:離脱治療施設のカルテに記録された新たな症状について、裁判官は決して取り上げようとしなかった。例、ミオクローヌス反射、筋肉運動協調の喪失、顔面のピリピリ感、頭部の筋肉の硬直(頭の周りをバンドできつく縛られた感覚)、油っぽい体臭 – 腺の反応など。
- 事実と異なる解釈:裁判所は、私が処方されたベンゾジアゼピンの用量が、治療中、ずっと同じであり、また薬物の増量を求めなかったことから、私には耐性が形成されておらず、よって中毒ではなかったと結論付けた。しかしながら、この見解は当方の主張と相反するものである。当方は「治療中に、薬物の増量を求めること」ではなく、「治療中に、離脱症状を生じていたこと」を耐性の根拠として主張していた。このことから、 DSM-IV-TRの診断基準4 「制御不能」が本件に適用されたが、判決でこの事実は無視された。
- 非科学的な用語(診断名)採用:「自律神経失調症」という別の診断を下すことに、薬物依存症を除外するための妥当な医学的・科学的根拠は存在しないも拘らず、裁判所は、私の薬物依存を否定する決定的な要因としてこの診断を認めた。
- 経過関連事実否認:例、BZ系薬剤の投与開始から6ヵ月後の時点で、初めて、自律神経失調症という診断が付けられた事実。
- 事実関係の誤り:BZ依存症(中毒)自体がストレスや不安症また自律神経の亢進およびそれに伴う関連症状を引き起こす(所謂自律神経失調症)。
- 偏った情報採用:高裁が、中毒を引き起こすとみなされるBZの用量を決める際には、製薬会社が作成した添付文書(多くの欠点に満ちたもの)に信用を置いた。
- 信憑性の高い証拠不作用:臨床用量の投与といえども2週間から4週間以上定常的に服用しているとBZ依存症に陥ってしまう可能性が十分にあること、そして実際に依存症に陥ってしまう事実が記載されている余地のない専門家による証拠を無視した。
- 証人尋問申請却下:当方の重要な証人である依存症の診断医(薬物中毒治療科医長)の証人尋問を2回申請したにも拘わらず、その申請は正当な根拠が示されることもないまま却下され裁判が続いた。
- 説明義務違反の不合理な反論:被告医師が下した元診断「中脳水道症候群」と、その当時に処方された薬剤は整合性が取れないのだが、裁判官はその矛盾は追及することはなかった。それどころか、「自律神経失調症」についても、同被告医師が裁判開始前にはその診断をしたことがなく、裁判開始後になって初めて主張し出したのだという事実も顧みられることはまるでなかった。
- 経過観察義務違反の不合理な反論:裁判官は、「平衡感覚を観察するための定期検査」と、「服用中に起こり得る依存形成について適切な経過観察」の違いを区別しなかった。
- 欠陥を有する裁判:訴訟中に裁判長の交代があった。その結果、本件について詳しい裁判長の代わりに、本訴訟の経過やBZ系薬剤についての基礎知識を全く持っていない新しい裁判長が途中で本訴訟を引き継ぐことになってしまった。
- 関連事実の除外:注目すべき点は、考えられないほどに強烈なストレスであるはずの日本での裁判手続きの期間中でも私の健康状態はどんどん良い方向へ向かっていったこと。私の健康状態を示すこの事実は、私の症状が単に不安神経症/ストレス(自律神経失調症)からくるものであり、また私にはその体質であるとする被控訴人側の主張を覆すに十分なもの。その理由、ストレス(自律神経失調症)になりやすい体質で、ストレスに苦しんでいる人が強烈なストレス環境の中で健康状態が回復するなんてことはあり得ないからである。これでは全く理屈に合わない。この事実も判決には含まれていなかった。
- 最終弁論:最終陳述書の末尾に、「9ヶ月間に渡り、中毒性の強いBZを処方内服された後、私は薬物中毒リハビリ施設で治療を受けることになった理由は何だと思っていますか?」と質問を投げかけた。答えはないまま裁判は終わってしまった。
(世界のトップ2の専門家は?)
BZ治療中及び投与量の減量中、また断薬後にみられた、ウェイン・ダグラスの症状(ジャドソン医師の報告書に記録されている)のほとんど全ては、依存症及び自律神経系の活動亢進によるものであり、これらは、このような状況でよく起こるものである。ヘザー・アシュトン教授(英国、ニューカッスル・アポン・タイン大学名誉教授、臨床精神薬理学)
親愛なるウェイン、あなたは間違えなく裁判による誤審を受けました。深く同情する次第です。敬具、マルコム・レイダー教授。大英勲章第4位、法学士、博士号、医学士、科学博士、英国精神医学会フェロー、英国医学アカデミーフェロー。英国ロンドン大学精神医学研究所名誉教授(臨床精神薬理学)。
ページトップに戻る
高等裁判所の判決における決定的な矛盾は、私がDSM-IV-TR の診断基準に適合する薬物依存であったという事実を除外していない点にあります。DSM-IV-TRは世界的にも認められている診断基準です。このDSM-IV-TR基準が、本訴訟全体の基礎になっていました。
DSM-IV-TR の7つの基準のうち、3つの基準に該当しさえすれば足りるところ、私の場合は、5つの基準に該当している、と主張しました(中毒治療科第1報告書2.3項目参照)。
裁判官は「耐性」(基準1)と離脱症状(基準2)の2つだけにしか見解を示しませんでした。しかも、その見解はDSM-IV-TRの診断基準に基づくものではありませんでした。基準を満たしていた残る3つの基準については、裁判所は全く判断しないままになっています。
その3つの基準は次の通りです:基準4「制御不能」、基準6「生活への打撃」、基準7「有害であることを知っているにもかかわらず使用を継続したこと」(中毒治療科第3報告書の第2章参照
7つの基準のうち、3つの基準を充足すれば依存症だと診断されることから、裁判官が重大な判断の誤りを犯していることは明らかです。その結果、DSM-IV-TR 診断基準を踏まえて控訴人である私が臨床的にベンゾジアゼピン依存症であったという事実を除外できてはいないのです。
ページトップに戻る
注 記
被控訴人は、東京高等裁判所の判決の第2.3.2のアに記述されているように、「DSM-IV-TRの物質依存の基準の適用例として挙げられている物質はコカイン,アルコール,喫煙である」との趣旨を主張しているが、DSM-IV-TRの診断基準は臨床用量内のベンゾジアゼピン系薬剤にも適用されます。このことはJudson 医師からの書簡による証言で証明されています。
高等裁判所での判決は、基本的に「耐性」と「離脱症状」に関する争点に基づいて行われました。判決では、私が耐性、離脱、薬の副作用に原因があると訴えていた症状は「自律神経失調症」の症状でも起こり得るため、私がベンゾジアゼピン依存となっていたことが立証されていない、ということになりました。
つまり、私の症状は薬物耐性や離脱症状からくるものではなく、ストレス症候/不安障害からくるものであると相手側が主張し、そして裁判官はこの主張を支持したのです。
判断の根拠として、裁判官はたった5つの症状だけを抜き出し、さらにその中の2つだけを選び出して薬物耐性と離脱症状または副作用に関連するものとしています。この裁判官が注目した2つの症状は、「熱に対して敏感になったこと」と、「口の潰瘍ができやすくなったこと」です。
この解釈では、20以上もの新たな症状が治療中に生じたという当方の主張が全くもって捻じ曲げられてしまっています。
診療中に現れた新たな症状については、中毒治療科第3報告書2.1.3項目には、動悸を含めて2つの症状が記録され、同報告書の2.2.3項目には、12の症状を新たな症状として表中に記載されています。表中の状況欄には「新たな症状」として表記されているので、初めての発症の意味をしています。
情緒不安定(パニック発作,気分動揺など)を含むその他の新たな症状については、中毒治療科第1報告書1.4.7項目に記載されています(情緒不安定の症状についての詳細は、中毒治療科第4報告書2.4.5~2.4.8項目に記載されています。)
新たに現れた視覚障害についての記述は、中毒治療科第4報告書3.3.12にあります。
ジャドスン医師が中毒治療科第3報告書2.2.4項目で指摘しているように、上記症状は、以前にはなかった新たな症状で、それまでのどのカルテにも記録されていない事実から証明できます。
判決理由の記載の中身をみると、上記症状に関する精査が行われていないことは明らかです。すなわち、(A)過去のストレスによる症状、(B)発端となっためまい発作による症状、(C)診断未確定のめまい発作に対する不安の症状、(D)ベンゾジアゼピン依存症による症状のそれぞれの関係を配慮せずに、裁判官が判断をしたのです。
更に、裁判所は、私が処方されたベンゾジアゼピンの用量が、治療中、ずっと同じであり、また薬物の増量を求めなかったことから、私には耐性が形成されておらず、よって中毒ではなかったと結論付けました。
しかしながら、この見解は当方の主張と相反するものです。当方は「治療中に、薬物の増量を求めること」ではなく、「治療中に、離脱症状を生じていたこと」を耐性の根拠として主張していました。事実、私は減薬しようと試みましたが不成功で終わりました。減薬試行の経緯については中毒治療科第4報告書1.5.1項目の「漸減試行の内訳」にまとめてあります。
このことから、DSM-IV-TRの診断基準4 「制御不能」が本件に適用されましたが、判決でこの事実は無視されました。
第1審決裁後の反証提出期限を過ぎてから、地方裁判所の裁判官は「耐性が生じなかった」という見解(詳細は後述)を提出し、当方には反証提出の機会すら与えられなかったために、被告側に有利な結果となりましたが、東京高等裁判所の裁判官は、その判断を採用・維持しました。
地方裁判所の裁判官が不当にもおこなったこの問題見解は、具体的には次の通りです。私が継続して服用していた薬剤の量が、次の処方日までに必要な処方量より不足していたと推定できる特定の期間があったことから、薬がなくても普通に生活できた期間があったはずだと言うのです。そして、同時に、このことはベンゾジアゼピン依存症ではなかったことを証明できるというものでした。
しかし、東京高等裁判所に控訴した後、処方箋、調剤明細書、領収書、カルテなどを踏まえて詳しく見直したところ、治療の初期段階には余剰薬が生じていたため、依存症であったにも関わらず、薬が足りなかった時にその余った分を使って治療期間を乗り切った可能性が十分にあった事実を立証したのです。
実は、原告第3陳述書A項目と、中毒治療科第3報告書3.2項目で上記のことは処方されたすべての薬量の詳細とともに既にはっきりと説明していた事柄だったのです。
ページトップに戻る

裁判でもう一つの争点となったのは、私が処方されていたベンゾジアゼピンの一日分の用量が依存に陥るほどの高用量であったかどうかということでした。高裁が、中毒を引き起こすとみなされるベンゾジアゼピンの用量を決める際には、製薬会社が作成した添付文書に信用を置きました。
裁判所は上記判断の際、提出された十二分なまでの文献と疑う余地のない証拠を、あろうことか、無視したわけです。私が提出した文献および証拠には、臨床用量の投与といえども2週間から4週間以上定常的に服用しているとベンゾジアゼピン依存症に陥ってしまう可能性が十分にあること、そして実際に依存症に陥ってしまうという事実が記載されていました。
証拠として提出した文献は下記のものを含みます。
- アシュトン教授による文献(アシュトン教授は世界を牽引するベンゾジアゼピン依存症に関する研究の第一人者である)。
- アシュトン教授の見解を一部引用(中毒治療科第3報告書2.1項目に記載)した文献。
- 「Benzodiazepineの常用量依存」と題する論文(北里大学・村崎光邦教授)を含む日本の文献など。
証拠(薬剤の添付説明書)を間違えて引用
先ず、裁判は製薬会社が作成した添付文書に信用を置いたことは十分におかしいと思われますが、さらに、その内容を誤って引用しました。
高等裁判所の判決は「...控訴人に処方されたベンゾジアゼピン系薬物であるリボトール及びコントールの各添付文書には大量連用により薬物依存が生ずる可能性があることの記載があるのみであり,臨床用量の投与による薬物依存の可能性に関する記載はない...のであるから...ベンゾジアゼピン系薬剤の臨床用量の服用により依存症が発生することは,我が国における医学的知見として確立していたものと認めることはできない。」ということになりました。
しかし、同各添付文書には「また、大量投与又は連用中における投与量の急激な減少ないし投与の中止により...等の離脱症状があらわれることがある...」という記載もありました。
後者には「又は」という単語が使われています。つまり、連用のみでも離脱症状があらわれることがあるという意味になります。注:離脱症状は薬物依存となっていることが前提条件です。添付文書の内容はとても曖昧ですが、要するに、連用中(いわゆる臨床用量)でも依存症が生じうるということです。
アシュトン教授:「もしベンゾジアゼピンが定期的に2~4週間以上にわたり服用されるならば、耐性と依存が生じる可能性がある。最小投与量はなく、例えば耐性と依存は2.5mg~5mgのジアゼパムの定期的な服用後に見られたこともある。」
ページトップに戻る

判決の2.3.1のイ項目では、当方が主張する「インフォームド・コンセント」を裁判官は次のように解釈していたようです。「“副作用などが結構あり得るので、何か具合が悪かったら、すぐ言ってほしい。”と医師が患者に説明する義務がある」。
また、当方が主張する「経過観察義務」については、裁判官は次記のように解釈していたようです。「“治療効果がみられない場合、6か月以上の長期使用を避けるべきである”ということで医師が経過観察する義務がある」。
しかしながら、上記2つの定義は、簡略化しすぎて内容的にも大きく削られてしまっています。本来の定義は中毒治療科第4報告書第4章で明確に説明されていました。
私はベンゾジアゼピン依存症であったことを立証する必要があったのは勿論のことですが、「インフォームド・コンセント」と「経過観察義務」も本訴訟の重要な争点でした。なぜなら、この2点について医師に過失があったことが判明すれば医師には責任があること(つまり因果関係)を立証できるからです。できなければ訴訟は成り立ちません。
証拠はインフォームド・コンセントはなかったことをしっかりと物語っています。なぜなら、「中脳水道症候群」という医師の診断結果とそのときに処方された薬が明らかに矛盾しているからです。
また、薬物依存の可能性を考慮した経過観察が全くなされなかったという事実は、カルテのどこを見てもこれに関する記録がないことではっきりとわかります。
判決文で、裁判官は被控訴人の行った「各種検査」や「通常検査」について何度も言及しています。この「検査」は私が依存症であったはずがないという医師側の主張の根拠となっていました。「検査」の結果では薬物依存を示す兆候は何も見られなかったので私が依存症であったはずがないと被控訴人はいうのです。
しかしながら、これら「各種検査」や「通常検査」の全てはめまいについてのみ対象にした検査(被控訴人のいわゆる「中脳水道症候群」に起因するめまいのための検査)だったのです。そして、薬物依存を対象にした検査を行ったというカルテの記録は全くありませんでした。
この事実については、中毒治療科第4報告書第4章で詳しく説明されていました。
ページトップに戻る

最初に起訴した時点では、私がベンゾジアゼピン系薬物の依存症であったか否かということだけを立証する裁判になると考えていました。
しかし、相手側の要望と裁判所の指示により、最終的には私の症状がベンゾジアゼピン系薬物の依存症であったのか、または「自律神経失調症(症候性のストレス/不安神経症関連病状)」であったのかを証明する裁判となりました。
高等裁判所は私の主張を認められないと判断しました。なぜなら、私の症状は「自律神経失調症」の症状としても捉えられる、つまり、私の症状が処方薬による依存がもたらしたものなのか、またはストレスや不安障害からくるものなのか見分けられないというのが高等裁判所の見解になったのです。
しかし、「薬物依存症」と「自律神経失調症(症候性のストレス/不安神経症関連病状)」はどのように見分けられるのかという質問は以前にも出されていて、その質問にはアルコール・薬物依存症専門治療センターの医長が中毒治療科第3報告書3.3項目(鑑別診断)でしっかりと説明したのです。
その説明には次のことが記述されていました。全ての症状は全体的臨床像およびDSM-IV-TR基準の適用を含み全体的に考究される必要があります。また、症状パターンも分析される必要があるということです。例えば:初期にいくらかの症状が落ち着いたこと、その後の症状のぶり返し、悪化(症状の強度、頻度、持続期間、性質などの推移)、薬物治療中また漸減治療中に表れた新たな症状、漸減治療後の回復などです。
耐性、離脱症状、副作用、症状パターンなどに関する情報に加え、本訴訟全体の骨格を成すDSM-IV-TRの診断基準や全体的臨床像に関するすべての詳細情報は十分に提供していました。全体的臨床像は下記の事実を含みます:
- 神経性疾患、精神性疾患などの病歴はなかったこと
- 単に処方期間と処方量だけで、少なくとも50~100%の確率で依存状態にあったことを断定することができる(中毒治療科第3報告書1.3.2項目)
- ストレス・不安および「自律神経失調症(自律神経系の機能亢進)」とその関連症状はベンゾジアゼピン依存によって起こし得ること
- 医師の治療中に新たな症状が数多く現れたこと(耐性と離脱症状)
- 過去に自律神経失調症の病歴は一切ないこと。ベンゾジアゼピン系薬物の投与開始から6か月をすぎて、初めて、自律神経失調症という診断が付けられたこと
- 薬物治療から逃げようとして、6か月後に転院したこと。
- 生活に影響があったこと(生活への打撃)
- 処方された薬を服用すると自分に有害であるとの自覚があったが使用を継続したこと。(有害であることを知っているにもかかわらず使用を継続したこと)
- 治療開始前に、まだ日本でなお勤務し続けることができていた事実であるが、治療後は仕事をこなすことができなくなったため、雇用契約の最後の1週間は仕事を全うすることができずニュージーランドに帰国を余儀なくされ、結局1年以上の間、全く就労することができない状態になってしまったこと
- アルコール・薬物依存症専門治療センターで1年以上もの期間に及ぶリハビリテーションを受ける必要になったこと
- 減薬治療中に、さらに新たな離脱症状が現れたこと。(離脱症状)
- 医師の処方薬を断薬してから1年以内で、発端であった症状も含めて、すべての症状から回復したこと(遷延性離脱症候により離脱が長引いた症状もいくつかあったが)
- 自分の足で立つことさえ難く、体重が病的と言える64kgから筋肉のついた84kgの身体に変身し、180㎏負荷のスクワット、ベンチプレス100㎏(のちに120㎏)、そして10時間に及ぶ山中ハイキングもできるようになったこと
- 断薬後、身体機能も精神機能もすべて回復し、再び日本に渡り、仕事と生活をこなす能力を取り戻すことができたこと
- 継続する賠償訴訟による更なるストレスの下にいるにも関わらず、以前よりずっと良い健康状態を維持し、日本での生活もこなし続けられたこと
*上記のことは患者カルテや証人の陳述書などの証拠によって立証されています。(「裁判のセクション」を参照)
診断における注意点は中毒治療科第3報告書1.2項目にしっかりと説明していたにもかかわらず、高等裁判所は上記のことを完全に無視した状態で判決を出してしまったのです。DSM-IV-TRの診断基準のうち3つについては全く言及されておらず、臨床像全体の記述についても全く検討されませんでした。
相手側の主張には、私には、先天的な慢性不安障害があり、ストレスや不安障害になりやすい体質であるというのがありました。
その主張に対して、アルコール・薬物依存症専門治療センターの医長は、上記(1)、(5)、(13)、(15)、(16)をもとに判断すれば被控訴人の主張は成り立たないことは明白であると結論付けています。
ページトップに戻る
重要点
注目すべき点は、中毒治療科第3報告書3.1.9項目でも指摘されていますが、考えられないほどに強烈なストレスであるはずの日本での裁判手続きの期間中でも私の健康状態はどんどん良い方向へ向かっていったことなのです。
私の健康状態を示すこの事実は、私の症状が単に不安神経症/ストレス(自律神経失調症)からくるものであり、また私にはその体質であるとする被控訴人側の主張を覆すに十分なものです。
その理由、ストレス(自律神経失調症)になりやすい体質で、ストレスに苦しんでいる人が強烈なストレス環境の中で健康状態が回復するなんてことはありえないからです。これでは全く理屈に合いません。
このように上記のことは明白であるのに高等裁判所の判決には含まれませんでした。
判決の第3節で裁判所は、私の症状が自律神経失調症に起因するものであるという被告側の主張を、繰り返し支持しています。
「自律神経失調症」とは日本で一般的に使用される診断用語であり、次の場合ではよく使われているようです。(A)心因性の症状であり、さまざまなストレスや不安から引き起こされる。(B)種々の自律神経系の不定愁訴であり、特に原疾患を特定できない場合に用いられる。
皮肉なことに、ベンゾジアゼピン依存症は自律神経系の機能亢進とともに上記(A)と(B)の両方とも引き起こすのです。
それゆえ、この曖昧な被告側が用いる用語を信憑性の高い根拠として裁判所が受け入れてしまっていること自体、根本的に間違っている上、誤解と混乱そして誤審を招く大きな要因となっているのは確かです。このことは、まさに、アシュトン教授のいう「おかしな考え方」のひとつの例であるといえるでしょう。
しかも、「自律神経失調症」と診断されたのはベンゾジアゼピン処方開始後7か月経過してからのことです。そのとき初めて「自律神経失調症」と診断されたのです。この事実を裁判所は全く配慮しませんでした。
アシュトン教授が立証しているように、ベンゾジアゼピンは中枢神経系および中枢神経系によってコントロールされている自律神経系(交感神経と副交感神経)を含む神経系全体に影響を及ぼします。ベンゾジアゼピンを服用すると、はじめは神経系の機能の低下がみられますが、常用するようになると耐性が生じ、神経系全体に機能亢進がみられるようになります(上告理由書の別紙5A参照)。
アシュトン教授は次のように続けます。「自律神経系は、あらゆる原因により引き起こされる不安やストレスに反応します。ベンゾジアゼピンに対する耐性の形成や、ベンゾジアゼピン依存症および離脱の全てがストレスや不安を引き起こすため、その時の自律神経系の反応は、他のいかなる種類の不安に対する反応と同じです」(上告理由書の別紙5D参照)。
上記のアシュトン教授のコメントを受け取ったのは、残念ながら、高等裁判所の判決後でしたが、ジャドスン医師が既に以下のことを説明していました。ベンゾジアゼピン依存症は、薬としてのベンゾジアゼピンが治すべき症状と全く同じ症状を引き起こすことがある。例えば、不安障害を治そうとしてベンゾジアゼピンを服用するのだが、服用してしまったために不安障害およびその関連症状を発症するといった具合。ストレスからくる症状とベンゾジアゼピン依存症の症状の些細な違いを診断して見分ける方法の詳細(中毒治療科第3報告書3.3項目)。
裁判官はこのことについてまったく考慮せず、判決にも反映されていません。
ページトップに戻る

当方は、重要な証人であるジャドスン医師(依存性薬物の専門医)の証人尋問を申請しましたが、地方裁判所においても、高等裁判所においても、2回とも却下されました。よって、ジャドスン医師の報告書の内容やその中に記述のあった争点についての詳しい説明をすることができなかったし、同医師が弁護側に直接質問する機会もありませんでした。
ジャドスン医師は診断医であり、本訴訟に関わる唯一の依存性薬物分野の有資格者であり、経験も豊富な医師であったのです。
ページトップに戻る

以下は、私の弁護士が当時送ってくれていた定期メール(各弁論準備手続期日終了後のもの)による報告からの抜粋です。裁判官らの本訴訟に対する姿勢をうかがい知ることができると思います。
下記は、平成21年12月1日午前10時30分、東京高等裁判所第9民事部書記官室(16階)にて、開かれた第1回進行協議期日についての報告書からの抜粋です。
「裁判所の構成は3名となります。今回は,内1名(恐らく右陪席)が出て来て,色々と聞きました。不勉強な裁判官で,記録を何も読んでいませんでした。”“この裁判官ほど,不勉強な高裁裁判官に会うのは,私は,はじめてです。」
下記は、平成22年3月25日午前11時40分に開かれた高裁第4回期日(第3回弁論準備手続期日)についての報告書からの抜粋です。
「左陪席は,裁判長のようにテキパキと訴訟指揮できませんから,時間が沢山かかるのは当然なのです。しかし,大坪裁判長が転勤となれば,それはそれで,後任の裁判長がどんなふうに出て来るかという不安が残ります。」
「大坪裁判長は,事件の筋を正確に見切ろうとする姿勢が顕著で,当初の左陪席のように,「あんたたち1審で負けたんでしょ。2審でも負けが推定されるよ。」などと安直に出る所は皆無だったのですが,すべての裁判官がそんなふうではありません。」
上記に加えて、資料を準備するための十分な期間は全くもらえませんでした。2つの異なる国、そして2つの異なる言語を用いての資料作成のための時間的考慮はなされなかったのです。通常通りに、厳しい提出期限が決められていました。残念ながら翻訳にかける十分な時間はありませんでした。
このことは原告第3陳述書L項目と、中毒治療科第3報告書3.5.4項目で裁判所にお伝えしてありましたが、対応することはありませんでした。
結局、十分な時間が取れなかったことから、提出資料の多くに翻訳の誤りがあり、原文の英語とは異なる表現がいくつもみられました。当然のごとく、提出資料の品質は到底満足のいくものではなく、誤解を招きかねない内容もありました。(「誤訳を参照」)
ページトップに戻る

上記「DSM-IV-TRの適用」で述べたとおり、裁判官は診断基準のうちの3つについて検討しなかった。その3つは以下の通りです。基準4「制御不能」、基準6「生活への打撃」、基準7「有害であることを知っているにもかかわらず使用を継続したこと」。
診断基準4については、「減薬・断薬試みの失敗の連続であった」ということから充足した。診断基準6については、「治療後の就労不能、社会的能力の喪失、人間関係の不全、恋人との人間関係の不全、娯楽活動に参加する能力の喪失がみられた」ということから充足した。診断基準7については、「薬は有害な影響を与えている可能性があるとの自覚があって、それを医師に訴えたが、やめることができなくて処方通りに服用し続けた」ということから充足した。
*上記のことはカルテや証人の陳述書どの証拠によって裏付けられていました。
裁判官は、アルコール・薬物依存症専門治療センターの医長からの提言についても無視しました。その提言は、以下のとおり、診断の際に留意すべきことです。「これらの診断基準を適用する際に気を付けるべきことは、各基準を一つずつ個別にみてしまってはいけないということです。むしろ、全体的臨床像の中で、それぞれの基準の関係を考慮しながら検討されなければいけません」(中毒治療科第3報告書1.2.2項目参照)。また、「診断基準を正しく用いるには、問題全体について熟考したうえで、洞察力と判断力を要します」(中毒治療科第1報告書2.1.1項目参照)。
当方の重要証人である医長(診断医)は、裁判での証人尋問を2回拒まれています。1回目は東京地方裁判所で、2回目は東京高等裁判所においてです。
その結果、本訴訟における唯一の依存性薬物の専門家として、裁判において上記の必要な洞察力と判断力を発揮する機会はなく、被告側に反対尋問することもできないまま裁判が終わってしまったのです。
上記の忠告(診断基準を適用する注意点)には耳を傾けず、裁判官は審議を進め、判断を下してしまいました。私が依存状態にあったか否かということについて特定の症状だけを取り上げ、単純に決めてしまったのです。しかもその取り上げた症状についても全体を見ようとせず、一部分だけを抜き出し、大幅に省略してしまったり、誤解に満ちたものになっていました。
さらに、中毒治療科第3報告書2.2.9項目に記述された「薬物依存症専門治療センターでの減薬治療中に生じた新たな症状」について、裁判官は決して取り上げようとしなかったのです。
「耐性」と「離脱症状」には個人差があるという厳然たる事実があるにもかかわらず、このことについて考慮されることは全くなかった。このことは薬物依存症専門治療センターの医長の第5報告書(最終報告書)に詳しく記述されているのだが、この報告書を裁判所に提出する機会を与えられることはなかった。
事実だけを客観的に捉えることが裁判所にできていれば、残る2つの診断基準(DSM-IV-TRの診断基準3と5)についても私に該当するという事実に気づいたはずである。
「その物質(ベンゾジアゼピン)をはじめのつもりより長い期間使用した」ということから基準3を適応することは可能で、「ベンゾジアゼピンからの回復に費やされる時間が多かった」ということから基準5を適応することは可能である。このようにきちんと見ていけば、7つあるDSM-IV-TR診断基準のすべてに該当することがわかる。
被告医師が下したもともとの診断「中脳水道症候群」と、そのときに出された処方は整合性が取れないのだが、その矛盾は追及されることはなかった。それどころか、「自律神経失調症」についても、同医師が裁判開始前にその診断をしたことがなく、裁判開始後になって初めて主張しだしたのだという事実も顧みられることはまるでなかった。
裁判所はベンゾジアゼピン系薬物の中毒性について判断する際、専門家による十二分なまでの文献と疑う余地のない研究結果を無視して、製薬会社の製品パッケージに書いてある説明書にのみ重きを置いたのである。
訴訟中に裁判長の交代があった。その結果、本件について詳しい裁判長の代わりに、本訴訟の経過やベンゾジアゼピンについての基礎知識を全く持っていない新しい裁判長が途中で本訴訟を引き継ぐことになってしまった。
裁判の最終段階において、改めて精密検査を受けさせてくれと迫った(原告第3陳述書H項目)。検査を行う病院は裁判所が指定する任意の病院で構わない、そうすれば被告の主張する「自律神経失調症(症候性のストレス/不安神経症関連病状)」であるのか「中脳水道症候群」であるのかはっきりするではないかと宣言したのである。
最終陳述書(原告第4陳述書14項目)の最後に、「9ヶ月間に渡り、中毒性の強いベンゾジアゼピンを処方内服された後、私は薬物中毒リハビリ施設で治療を受けることになった理由は何だと思っていますか?」と質問を投げかけた。
答えはないまま裁判は終わってしまった。
ページトップに戻る

本件は医療行為が原因で引き起こされたベンゾジアゼピン系薬物依存症及びその関連障害には該当しないというのが東京高等裁判所の最終判断である。理由は、投与量を増やしてもらいたいという欲求もなく、実際に投与量は増えていないことから薬物耐性は形成されていない、また、耐性が形成されていないのだから離脱症状があるはずがないというのだ。続いて、「耐性」と「離脱症状」との主張を除外した。
治療中に行われた医師による定期検査はどれもこれも薬物依存症の経過観察のためのものではないという事実にもかかわらず、その検査結果をもとにして、治療中に私の症状が悪化したという可能性はないと裁判官は判断した。
ベンゾジアゼピン系薬物の依存性について高裁の裁判官は次のように述べた。「控訴人に処方されたベンゾジアゼピン系薬物であるリボトール及びコントールの各添付文書には大量連用により薬物依存が生ずる可能性があることの記載があるのみであり,臨床用量の投与による薬物依存の可能性に関する記載はないし,グランダキシンの添付文書には同薬剤自体による依存症の発生については言及されていないのであるから,原判決の説示するとおりベンゾジアゼピン系薬剤の臨床用量の服用により依存症が発生することは,我が国における医学的知見として確立していたものと認めることはできない。」
裁判官は結論付けた。「控訴人が訴えた症状は、飛文症以外のものは自律神経失調症として説明できるものであり、自律神経失調症は、症状が発現したり消失したりし、また、症状も転々と変わるというように、症状が定まらないのが一つの特徴とされているのであるから、これらの症状をもってベンゾジアゼピンの耐性の結果の症状であると直ちにいうことはできないものである。したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」
ページトップに戻る

高等裁判所の判決が出たのは2011年2月11日(東日本大震災と福島第一原発事故のちょうど1か月前。この約5年前から福島での生活を始めました。)
判決受領後、すぐに最高裁判所への上告準備に取り掛かりました。上記事故により第2の故郷である福島を離れなければなりませんでした。福島第一原発で一回目の水素爆発が起きた2011年3月12日のことでした。
この時点ではもう弁護士はいなかったので、最高裁への上告理由書を私一人で書き上げることになりました。その書類の分量は、裁判官など9名分の上告理由書と関連書類などシューズボックス丸々1杯分となりました。
余震、放射能漏れ、計画停電で世の中が揺れ動くなか、避難先を転々と移動しながらも、日本語で書き上げるべく、黙々と作業を続けました。ろうそくの明かりをたよりに作業を続けたことも度々ありました。職も失い、一時的には住む場所もない状態での作業でした。
最高裁が決定を下したのは2011年10月13日。上告は棄却されました。上告をすることが許されるのは「憲法違反」の場合だけですが、本件の上告理由はそれには該当しない、というのが最高裁の判断でした。
法廷で証人尋問に参加する機会を重要証人に与えないという行為は「憲法違反」に該当するのではないかと、裁判所事務官に連絡を取った際に質問したところ、その答えは次の通りでした。「証言をする機会を与えるか与えないかの判断は裁判官の自由裁量に任せられている。」
ページトップに戻る

世界の権威たちは?
ヘザー・アシュトン教授
ベンゾジアゼピン治療中、投与量の減量及び離脱の間における、ほぼ全てのウェイン・ダグラスの症状(ジャドソン医師の報告書に記録されている症状)は依存症及び自律神経系の活動亢進によるものであり、これはこのような状況ではよく起こることです。ダグラス氏が2000年3月に転職した後に自然に解消した身体的ストレスの軽度のエピソード以外、ベンゾジアゼピン服用以前の“Autonomic Nervous Disorder”の証拠は報告には何も見られませんでした。2000年5月の目まい発作は疑う余地もなく前庭神経炎によるもので、これはたいていウイルスが原因になります。
“…there was no question that you had ..” 私がここで意味したのは、貴方がベンゾジアゼピンを服用する以前に “Autonomic Nervous “Disorder” を患っていたというのは論外だ、ということです。すなわち、貴方がそれを患っていた筈はなく、それを更に検討する価値もなく、論点でもないということです(アシュトン教授の全ての所見を読む)。
ヘザー・アシュトン教授(英国、ニューカッスル・アポン・タイン大学名誉教授、臨床精神薬理学)
別府博圀医師
誤解を招く医学用語(自律神経失調症)であることは、裁判官も承知の上で書いているのです。そんなことは素人だって分かっているのです。
裁判官も、最初から、貴方(ウェイン・ダグラス)を敗訴にするつもりで、話を聞き、両方の言い分をきちんと聞いたふりをして、このように結論を導き出したのです。
自分たちの判決文の矛盾など、多分分かりすぎるくらい分かって書いているのです。まず、初めに結論あり、その結論になるように、論理をこねくり回して作りあげた判決です。言葉遊びをしているだけなのです。
専門家はこう言っている、添付文書にはこう書いてあるなどと、都合のよいことだけを証拠にして、貴方は薬のせいでこうなったのではなく、もともと自律神経失調症、あるいは日本での生活でストレスが多かったからこういうことになったのだと、書いているだけです。
読んでいるだけで、気分が悪くなるようなひどい判決です。
別府宏圀医師(薬害オンブズパースン会議)、東京大学医学部卒業、東京都立神経病院神経内科部長、新横浜ソーワクリニック院長、開業神経科、医薬品の監視、日本初の独立医薬品情報誌『正しい治療と薬の情報』(TIP)を創刊、前記の誌編集委員、NGO薬害オンブズパースン会議 (副会長)、NPO DIPEx-Japan、健康と病いの語り(理事長)、日本臨床薬理学会、日本薬剤疫学会名誉会員、主な著書に『医者が薬を疑うとき』訳書に『世界のエッセンシャル、ドラッグ─必須医薬品』、監訳書に『子宮頸がんワクチン問題』、監修書に『アシュトンマニュアル』
マルコム・レイダー教授(ベンゾ薬害訴訟世界第一人者)
親愛なるウェイン、
あなたは間違えなく裁判による誤審を受けました。深く同情する次第です。
敬具、
マルコム・レイダー
マルコム・レイダー教授、大英勲章第4位、法学士、博士号、医学士、科学博士、英国精神医学会フェロー、英国医学アカデミーフェロー。英国ロンドン大学精神医学研究所名誉教授(臨床精神薬理学)
ページトップに戻る
Consider This
In closing of this section, I invite you to ponder the following question. I wrote this at the very end of my final statement and it was the very last thing I had the opportunity to put to the Tokyo High Court before the verdict was handed down.
Quote
「9ヶ月間に渡り、中毒性の強いベンゾジアゼピンを処方内服された後、私が薬物中毒リハビリ施設で治療を受けることになった理由は何だと思われますか?」
また、ベンゾジアゼピンを断ってから、長期間かかりましたが、すっかり健康を取り戻したのは、なぜだと思われますか?
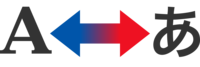
このサイトの主要言語は英語です。
その翻訳は私自身を含む複数の人によって手がけられました。
私の母国語は日本語ではありませんので何卒ご理解いただきたくお
「もし何かの薬を飲み続け、それが長い長い災難をもたらし、あなたからアイデンティティをまさに奪い去ろうとしているのなら、その薬はベンゾジアゼピンに違いない。」

ジョン・マースデン医師
ロンドン大学精神医学研究所
2007年11月1日
「我々の社会において、ベンゾは他の何よりも、苦痛を増し、より不幸にし、より多くの損害をもたらす。」
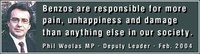
フィリップ・ウーラス下院議員
英国下院副議長
オールダムクロニクルOldham Chronicle (2004年2月12日)
「ベンゾジアゼピン系薬剤はおそらく、これまでで最も中毒性の高い薬物であろう。これらの薬を大量に処方してきた途方もなく大勢の熱狂的な医師達が、世界最大の薬物中毒問題を引き起こしてきたのだ。」

薬という神話 (1992)
「薬があれば、製薬会社はそれを使える病気を見つける。」
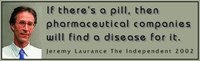
ジェレミー・ローランス (ジャーナリスト)
インディペンデント紙 (2002年4月17日)
「製薬会社に対して、彼らの製造する薬について公正な評価を期待することは、ビール会社にアルコール依存に関する教えを期待するのと同じようなものである。」

マーシャ・エンジェル医師
医学専門誌"New England Journal of Medicine"元編集長
「ベンゾジアゼピンから離脱させることは、ヘロインから離脱させるよりも困難である。」
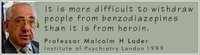
マルコム・レイダー教授
ロンドン大学精神医学研究所
BBC Radio 4, Face The Facts
1999年3月16日
「長期服用者のうち15%の人たちに、離脱症状が数ヶ月あるいは数年持続することがある。中には、慢性使用の結果、長期に及ぶ障害が引き起こされる場合もあり、これは永続的な障害である可能性がある。」

ヘザー・アシュトン教授
医学博士、名誉教授
Good Housekeeping (2003年)
国際麻薬統制委員会2010年報告書によると、日本におけるベンゾジアゼピン系“抗不安薬(anxiolytic)”の平均消費量は、欧州各国の多くよりも少ないものの、アジアの中ではイランに次いで最も多い(35頁、Figure 20参照)。

一方、日本のベンゾジアゼピン系“催眠鎮静薬(sedative-hypnotic)”の平均消費量は、ベルギーを除くと世界のどの国よりも多い(39頁、Figure 26参照)。
アシュトンマニュアル:世界的な専門家、ヘザー・アシュトン教授によって書かれた、ベンゾジアゼピン系薬剤と離脱法についての解説書。
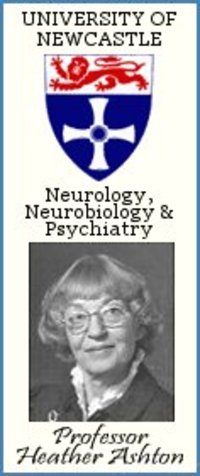
このマニュアル内で示された離脱スケジュールは単に“一般的な指針”を示すために作成されたものであることを、あなたの処方医に伝えることが大切です。離脱の経験は人それぞれで、同じものがない。離脱の経過は多くのファクター(要因)に影響されるからです。
臨床用量のベンゾでは中毒にならないと思っていませんか?

考え直しましょう!
“もしベンゾジアゼピンが定期的に2~4週間以上にわたり服用されるならば、耐性と依存が生じる可能性がある。最小投与量はなく、例えば耐性と依存は2.5mg~5mgのジアゼピンの定期的な服用後に見られたこともある。”
ヘザー・アシュトン教授(英国、ニューカッスル・アポン・タイン大学名誉教授、臨床精神薬理学)。
I went from being barely able to walk when I was on benzodiazepines to being able to squat 180kgs following abstinence and rehabilitation.
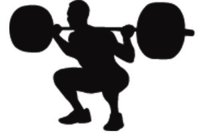
What are benzos for again?

The only time I’ve ever needed to visit a psychologist in my life was AFTER (wrongfully) being prescribed benzodiazepines…
Both the High Court and Supreme Court Verdicts dismissed my case completely (100%), despite the comprehensive medical reports, expert opinions, and credible evidence...

Who's protecting society (the tax payers) whose money they receive as salary to protect the public?
What worked well?
What didn't work so well?

For the interest of the reader, in this site I have given feedback on what worked well in my case and what could have been done better.
A lot of people were surprised that I did not bear a grudge against the prescribing doctor, but I felt anyone can make mistakes.

What got me though, was the fact he showed no remorse even after the evidence had been made clear.
Seems people are all saying the same things over and over…

- I was like a zombie
- It felt like I was in hell
- It was much harder to come off benzodiazepines than anything else I'd ever had before
- It took a chunk of my life away
- It has destroyed my life
- The doctor never told me they were addictive / The doctor told me they weren’t addictive
- When I complained my condition was worsening the doctor prescribed me more...
Cause for Alarm!

Consider this extract from:
A Review of David Healy's “The Psycho-pharmacologists III” by Professor Heather Ashton
How is it that the pharmaceutical industry has come to dominate the field?
Healy points out that drug companies “are now not simply confined to finding drugs for diseases. They have the power to all but find diseases to suit the drugs they have”.
Pierre Simon (Sanofi Pharmaceuticals) remarks: “In the beginning the pharmaceutical industry was run by chemists.
This was not so bad... Now most of them are run by people with MBAs... people who could be the chief executive of Renault, Volvo or anything.
They don't know anything about drugs.” The problem comes when a chemist presents an interesting drug to the financial analyst, who asks: “What is the market?”
The chemist has to decide for what indication the drug will be developed. If the indication is not there, it must be created.
このウエブサイトの左上に私の信条が掲げてあります。裁判を起こして活動をやり続けてきた私はクレジーだと思った人が多くいました。

しかしながら、私たちは二つの選択肢を持っている「何かをすることを選ぶ」か「何もしないことを選ぶ」-多くの人々に希望を持って生きることを与えるのはどちらでしょう?その選択権は私たちの手の中に…