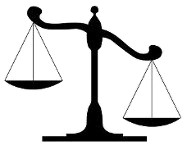ジャパンタイムズ紙の特集記事

注 記
この日本語記事は、2012年3月13日付のTHE JAPAN TIMES(英字新聞)記事を翻訳し、それにダグラスさんのコメントを最後のところに追記したものです。
2012年3月13日(火曜)ジャパン・タイムズ
ニュージーランド人敗訴 医療によってもたらされた深刻な薬物依存をめぐる争い
― ベンゾジアゼピンの危険性を訴える在日外国人 ―
(サイモン・スコット記者)

変わり果てた男:ベンゾジアゼピン中毒に苦しめられ、正義と賠償を求めて最高裁判所まで闘ったウェイン・ダグラスさん。最高裁は審理を拒否した。ダグラスさんによると、医師から“根治療法”の一環と言われ、ベンゾジアゼピンを7ヶ月間処方された。
(写真・文:サイモン・スコット)
ページトップに戻る
(衝撃)
2001年の初め、ウェイン・ダグラスさんが日本から母国ニュージーランドに帰国した時、空港で対面した母親は、最初、自分の息子と気付くことが出来なかった。
「私が死にかけのゾンビのように見えたと母は言っていました」
「母は、たった100メートル離れた病院に私を連れて行くのに、車で送っていかなければいけませんでした。当時の私はそこまで歩くことすら出来なかったのです」
ダグラスさんが日本からの出国を余儀なくされたのは突然であり、それは苦痛に満ちたものであった。ある日本人医師によって、安定剤の一種であるベンゾジアゼピンを依存性薬物と知らされずに処方され、酷い中毒に陥ってしまったのだ。
ダグラスさんは当時の様子を次のように振り返る。
「母国に帰る途中のある駅で、私は着ていた仕事用の衣服を全て脱いで、ゴミ箱に投げ捨てました。靴も含めて全てです」
「中毒の影響で体が穢(けが)れた気がして気持ちが悪かったのです。また、当時耐えていた苦痛を思い出させるものは全て携帯したくなかったので、持ち物全てを捨て去ることにしました」
付け加えると、彼の身体は処方薬中毒のために、軽い荷物を持ち運ぶことさえ困難なほど衰弱してもいたのだ。
ページトップに戻る
(中毒への道)
1992年、ダグラスさんは日本語で優秀な成績を収め、2週間の奨学金を得て初めて来日した。その後、様々な地方自治体の行政組織で英語教師や国際交流のコーディネイターとして働き、合計10年以上、日本で過ごしてきた。
2000年3月、ダグラスさんは財団法人埼玉県国際交流協会において、国際交流コーディネイターとしての勤務をスタートした。5月11日の未明までは、彼は公私ともに全てが順調に進んでいた。
「午前2時頃、突然、頭が揺れたり、回ったりするような感覚で目が覚めた後、目眩の発作に襲われました。目の前が回転する感じで、部屋が時計回りにグルグル回っているようでした」と、ダグラスさんは語る。
彼は上司に電話し、大宮赤十字病院までタクシーを手配してもらい、そこで検査を一通り受けた。検査結果はどれも異常なかったが、その間も奇妙で恐ろしい症状は続いた。目眩、火照り、足元のふらつき、吐き気、嘔吐、周囲が左右に揺れる感覚、酔っぱらったような感じ、頭や身体が揺れ動く感じ、などであった。
「歩くと、左にそれていくように感じました。誰かが左側に向かって私を押しているような感じです。歩行中はビデオカメラを覗きながら周囲を見ているような感覚でした」
その厄介な症状に消耗させられたダグラスさんは困り果てた。そして1ヶ月が過ぎた頃、テレビで偶然、目眩の世界的権威として紹介される医師が特集されているドキュメンタリー番組を観た。治療に望みをつないだダグラスさんは、その医師の診察を受けるため東京に向かう。
その医師はダグラスさんを「中脳水道症候群(シルヴィウス水道症候群)」と診断した。これは、中脳の外側溝(シルヴィウス溝)の狭窄により引き起こされる稀な疾患で、眼球運動の異常やその他の症状を呈する。ダグラスさんによると、医師は「この病気を治療するには、薬を使ってあなたの体質を構造的に変える必要がある」と伝え、その問題となる処方のことを“ドラッグ・カクテル(多剤併用療法)”と呼び、治療については「“ラディカル・アプローチ(根治療法)”を行う」と付け加えたという。
ページトップに戻る
(医師の処方とその後に起きたこと ―― 帰国へ)
そしてダグラスさんは5種類の異なる薬を処方される。3種類のベンゾジアゼピン系安定剤(コントール、リボトリール、グランダキシン)とトフラニールと呼ばれる三環系抗うつ薬、そして、ケタスという商品名で販売されている抗炎症剤(イブジラスト)であった。医師からは薬の性質について何の説明も受けなかったとダグラスさんは言う。
「念のため、それらの薬に何らかの副作用があるかどうか質問してみることにしました。すると医師は、『全ての薬には多少の副作用があります。しかしこれらは少量では依存性はなく、副作用もほとんどない薬だから、長期間飲んでも大丈夫です』と答えたのです」
ダグラスさんは当時ベンゾジアゼピンについて何も知らず、またその医師が平衡障害の権威であったため、医師の判断を信用して受け入れた。
治療を開始してから数週間後、ダグラスさんは状態が著しく改善し(∗1)、苦しんでいた酷い症状が落ち着くことを経験した。そこで処方される薬を飲み続けた。
しかし残念なことに、この回復は長続きせず、8月の終わり、つまり治療開始から2ヶ月も経たないうちに、ダグラスさんの状態は再び悪化する。医師が完全に回復するだろうと予想していた、治療開始から4ヶ月が経過するまでに、ダグラスさんの目眩は治療前に比べて顕著に悪化していた(∗2)。
「四六時中、酔っぱらったかのように足元がよろめく状態でした」
更に気掛かりなことに、彼は新たな症状も経験し始めたのだ。
「パニック発作、不安、気分の動揺、攻撃性、気が狂いそうな感覚など、酷い情緒の不安定に苦しみ始めました」
「このような感覚は初めて経験するもので、今でも残存しています(∗3)。精神的におかしいと診断されて、異国の地で施設に送られ二度と出てこられなくなることを恐れました」
2000年11月、ダグラスさんはその医師と彼の治療を信用できなくなり、処方薬を飲むことを止めることに決めた。しかしながら、ダグラスさんは、たった一回の服薬分さえ飲まずにいることが出来なくなっていることに気付いた。知らぬ間に、ベンゾジアゼピン中毒になってしまっていたのだ。
仕事をこなすことが次第に困難になり始めたため、上司はダグラスさんを軽い仕事に就かせ、一時間ごとに休憩させた。ダグラスさんはそれまでで最悪の状態に陥り、人生で初めて自殺を考えるようになった。
「一日24時間、一週間のうち7日、毎週毎週、毎月毎月、酔っぱらったかのようで、パニック発作など数えきれないほどの消耗する症状や、気が狂いそうな感じが全て同時に起きて、それが一年以上も続くのです。そんな中、何のサポートも受けずに異国の社会で普通に生きていこうとすることがどれほどのことか想像してみて下さい。その年の11月、母親に電話で、『お母さん、地獄にいるようだ』と言った時、私が何を伝えたかったか、少しは理解してもらえるのではないでしょうか」
日本では自力で対処できなくなったダグラスさんは、ついに2001年の3月、ニュージーランドに帰国することを決意する。ダグラスさんは帰国後地元の医師の診察を受けた時に初めて、日本で投与されていた薬には強い依存性があることを知った。そしてベンゾジアゼピン中毒と診断された。
ダグラスさんを診た医師は、彼をタラナキ基地病院のアルコール・薬物依存治療科に紹介し、4月には解毒治療プログラムに参加させた。そして2ヶ月足らずで、ダグラスさんはベンゾジアゼピンを絶った。
しかしながら、ダグラスさんの生活が正常に戻るにはほど遠かった。医師から復職を許可されるのにもう1年を要したのだ。そして現在に至っても、つまり10年経過しても、依存症による抑うつ、慢性的な不安、パニック発作など情動的な影響がある程度残り、今もなお悩まされることもあるという(∗4)。
「それからというもの、私は、このようなパニック発作などのために、普通の仕事をこなす能力が著しく低下し、その結果、自分の能力や経験に見合った仕事に応募することが出来なくなりました。結局、低賃金の仕事に応募するしかなかったのですが、それでも、すぐに疲労してしまうことがよくあったので、また仕事を失うことも時々ありました」と、ダグラスさんは語る。
ページトップに戻る
(医師の間違いに気付く)
長期にわたり、ベンゾジアゼピン中毒が収入やQOL(生活の質)に悪影響を与えたことを苦々しく思い、また、何故このようなことが自分の身に起きたのかを知ろうと、2003年、ダグラスさんは日本人医師の診断と薬物療法について調べ始めた。
「このようなことが決して二度と起きないようにするためには答えが必要でした。また、この過酷な経験に何らかの区切りをつけるため、身に起きたことを整理しつなぎ合わせることが、どうしても必要だと感じたのです」
そして、自身のケースを知れば知るほど、医療過誤の被害者であったことを確信するようになっていったダグラスさんは、賠償と正義を求める長い道のりを歩み始める。それはおよそ10年におよぶ長い道のりであり、最終的に彼は、最高裁判所の入り口まで行き着いた。
ニュージーランドそして日本で、神経内科医をはじめ他の専門家に相談したダグラスさんが、まず初めに気付いたことは、元主治医による中脳水道症候群という当初の診断は全くの間違いであり、また、たとえその診断が正しかったとしても、その疾患の治療にベンゾジアゼピンを用いることは全く不適切であるということであった。これらについて、全ての専門家の意見は一致した。
ダグラスさんがニュージーランドに帰国した際、彼を診察したオークランド病院の神経内科医、デイビッド・ハッチンソン医師は、ダグラスさんに当初見られた回転性や浮動性の目眩は、中脳水道症候群ではなく、急性前庭障害の発作に起因していた可能性が最も高いと断じた。これは、最初に埼玉の病院の医師たちによって下された診断と同じであった。
前庭障害とは前庭神経と呼ばれる、内耳から脳に情報を伝達する知覚神経が炎症を起こすことで発症し、目眩や吐き気、平衡失調を引き起こすことがある。
ハッチンソン医師は、裁判所に提出された報告書に添えられた2008年の書簡の中で、ダグラスさんには中脳水道症候群のいかなる神経学的兆候も示されていなかったことについて、次のように記した。
「より重要なことは、脳のMRI検査で、彼には中脳水道症候群を生じうる、水頭症あるいは他のいかなる疾患も示されなかったことである」
更にその書簡では、ほとんどの神経内科医にとって、中脳水道症候群とは現代臨床において、ほとんど使われることのない、かなり古い臨床概念と見なされているとも述べられていた。
そして、その誤診の疑いよりもショックだったことは、ダグラスさんに処方されていた薬が、彼に実際に発症していた疾患にも、誤診された疾患にも、どちらにも不適当なものだったという事実である。ハッチンソン医師はこう述べる。
「当職は、2000年のダグラス氏の治療において、ベンゾジアゼピン系薬剤が有効であろうと考えられた理由が、理論的にも、その他の根拠においても解らない。ベンゾジアゼピン系薬剤は、直接的に有効な制吐作用あるいは抗目眩作用を有しておらず、急性片側性末梢前庭障害(前庭神経炎)の治療に明確な有効性はない」
「更に、ベンゾジアゼピン系薬剤は、中脳水道症候群を生じうる、水頭症あるいはその他のいかなる疾患の治療にも効果はないと考えられる」
自身が経験したことをより理解し、長期にわたるベンゾジアゼピン中毒による苦痛の多くは避けられたことに気付き始めたダグラスさんは、次第に、正義と賠償を求めることを決意するようになっていった。
ページトップに戻る
(裁判)
2005年、不安や恐怖が大きかったものの、ダグラスさんは日本に戻り、元主治医に対して法的措置をとる準備に取り掛かる。そして2006年、元主治医および彼が勤めていた病院と、調停を開始した。しかし、解決に向けた数多くの試みは不調に終わり、2007年初め、ダグラスさんは東京地裁に提訴した。
裁判において、誤診の問題は争点とはならなかった。代わりに、損害賠償請求の基礎となったのは、インフォームド・コンセントなしに長期にわたりベンゾジアゼピンを処方され続けたために、ダグラスさんがベンゾジアゼピン中毒となったことと、元主治医が治療中にダグラスさんの状態に対する適切な経過観察を怠ったことであった。
元主治医の弁護士は、当初、ダグラスさんは決してベンゾジアゼピン中毒ではなかったと主張してきた。中毒になっていないなら、薬が有害作用を引き起こしていないことになるため、医師が薬に対する患者の反応を“適切に経過観察する”ことを怠っていたことにはならない、という反論であった。
結局、ダグラスさんは地裁で敗訴したものの、闘うことを止める気にはなれなかった。そして2009年、東京高裁へ控訴する。最終的に高裁は地裁判決を支持し、2011年2月、「控訴人の請求は理由がない」とする判決を下し、ダグラスさんの請求は棄却された。
高裁判決の基礎となったのは、ダグラスさんが耐性、離脱、薬の副作用に原因があると訴えていた症状は「自律神経失調症」の症状でも起こり得るため、ダグラスさんがベンゾジアゼピン依存となっていたことが立証されていない、ということであった。具体的には、ダグラスさんには元々不安障害があるとされ、それが原因となってこれらの症状が引き起こされているのであり、薬が原因ではないと結論付けられたのだった。
しかし、ダグラスさんのケースを調査した、ベンゾジアゼピン中毒の第一人者である、英国ニューカッスル大学のヘザー・アシュトン教授(向精神薬理学、名誉教授)によると、薬そのものが原因であったとのことだ。
アシュトン教授は「ベンゾジアゼピンは、神経系全体、つまり、中枢神経系および自律神経系の両方に影響を及ぼす」と指摘する。
自律神経系は、血管の拡張や収縮、心臓の鼓動など、不随意の身体機能を調節、制御する。例えば、恐怖を感じる場面では、自律神経系の働きにより、手の震えや心拍数の増加が引き起こされる。そして、アシュトン教授はこう述べる。
「自律神経系は、あらゆる原因により引き起こされる不安やストレスに反応します。ベンゾジアゼピンに対する耐性の形成や、ベンゾジアゼピン依存症および離脱の全てがストレスや不安を引き起こすため、その時の自律神経系の反応は、他のいかなる種類の不安に対する反応と同じです」
更に、裁判所は、ダグラスさんが処方されたベンゾジアゼピンの用量が、治療中、ずっと同じであったことから、彼には耐性が形成されておらず、よって中毒ではなかったと結論付けた。
しかしながら、ニュージーランドに帰国時、ダグラスさんを治療したタラナキ基地病院のグレアム・ジャドスン医師(アルコール・薬物依存治療科医長)は、裁判所に提出した報告書の中でこう述べる。
「長時間作用型ベンゾジアゼピンの場合であっても、単に耐性だけが原因となり、治療中(服薬中)にも患者に離脱症状が出現する可能性があることを明確にしておきたい。これは一旦患者に耐性が形成されると、同量のベンゾジアゼピンでは、たとえ血漿中濃度が同じであっても、同じ効果を発揮しないこともあるからである」
ここでジャドスン医師が言及しているのは、ベンゾジアゼピン中毒においてよく見られる現象で、“耐性離脱”と呼ばれる。通常の中毒のパターンにおいては、中毒者は、期待する心理効果を得続けたり、離脱症状を避け続けたりするために、時間をかけて徐々に薬の用量を増加させていく。
しかし、ダグラスさんの場合ように、中毒になっていても、薬の増量が起きず、全く同用量を長期間飲み続けているケースもある。このような時、たとえ薬をまだ使用中であっても、離脱症状が出現するのだ。
裁判でもう一つの争点となったのは、ダグラスさんが処方されていたベンゾジアゼピンの一日分の用量が依存に陥るほどの高用量であったかどうかということである。最も驚いたことは、高裁が、中毒を引き起こすとみなされるベンゾジアゼピンの用量を決める際、製薬会社が作成した添付文書に信用を置いたことであった。
この点について、高等裁判所の判決から引用する。
「控訴人に処方されたベンゾジアゼピン系薬物であるリボトリール(クロナゼパム)及びコントール(クロルジアゼポキシド)の各添付文書には大量連用により薬物依存が生ずる可能性があることの記載があるのみであり、臨床用量の投与による薬物依存の可能性に関する記載はないし、グランダキシンの添付文書には同薬剤自体による依存症の発生については言及されていないのであるから、原判決の説示するとおりベンゾジアゼピン系薬物の臨床用量の服用により依存症が発生することは、我が国における医学的知見として確立していたものと認めることはできない」
しかしながら、かねてから、臨床用量によるベンゾジアゼピン中毒の問題を認識していた日本の医療専門家もいるという証拠も存在する。
例えば、1996年まで遡ると、北里大学の村崎光邦教授が、「Benzodiazepineの常用量依存」と題する学術論文を発表している。
そこで村崎教授は、「4~6ヵ月以上の臨床用量のBZ服用者には50%を超える退薬症候の発現率を覚悟しておかねばならないことになる」、「本来、依存状態に陥る前にうまくBZの投与を終了して、6ヵ月以上の長期使用へ移動しないような予防的工夫が大切である」と述べている。
欧米各国の医療従事者の間では、臨床用量のベンゾジアゼピンで中毒になる可能性があること、また実際に高い頻度で中毒になっていることは常識として広く認められている。
前出のアシュトン教授によると、ベンゾジアゼピンが2~4週間以上にわたって常用された場合、耐性と依存が形成される可能性があるという。同教授は「依存形成されないという安全な用量はありません。例えば、一日2.5~5mgのジアゼパムの常用後に、耐性および依存の形成が見られたこともあります」と付け加える。ダグラスさんは、日本で、ほぼ7ヶ月間にわたり、ジアゼパム換算で一日21~31mgのベンゾジアゼピンを処方されていた。
最終的に、ダグラスさんは最高裁判所に上告しようとしたが、“憲法違反”にあたるとは言えないとみなされ、裁判所で審理されることもなく、2011年10月、訴えは退けられた。
裁判に負けたものの、ダグラスさんはまだ前を向き、こう語る。
「負けた気がしません。私は勝ち、裁判所が負けたと感じています。彼らは医師たちを守る一方、社会を守り損なったように思えます。私がやりたいことは、私の経験を紹介したり、裁判を通して集めた資料を使ったりして、依存患者や依存に陥る可能性のある人たちのために情報を提供することです」
日本でダグラスさんを治療した元主治医に、ダグラスさんのケースについて質問書を送り、コメントを求めた。医師がそれを受け取ったことは電話で確認できたが、この記事の公開までに彼が回答することはなかった。
ページトップに戻る
(日本の現状)
日本において、ベンゾジアゼピンの使用は増加している。一人あたりの使用量は、多くの欧州各国よりも少ないが、アジアでは依然として最も多い(∗5)。
2010年の国連による報告書では、日本における高レベルの消費量は、ある程度は高齢者人口の多さによるものだが、“不適切な処方のあり方とそれに関連する乱用”も反映していると考えられると指摘されている。
医薬品に関する専門家でもある神経内科医の別府宏圀医師は、日本のベンゾジアゼピン使用率が高いことは、製薬企業やメディアによって推し進められた“医療化社会”に向けたトレンドがより拡大されていることの一環と考え、次のように述べる。
「最近では、人々は病院や医師の元に行くようますます駆り立てられています。伝統的な日本社会では、近所の人の話に耳を傾け、世話をし、助け合っていました。しかし今日の日本では、個々がバラバラになり、家族は小さくなっています。その結果、人々は専門家に相談するようになったのです。このような社会の変化が、人々の不安を増大させています」
また、別府医師は規制の強化を推奨し、一度の最大処方日数を、現在ほとんどのベンゾジアゼピンの場合の上限となっている30日から1週間に短縮すべきだと述べる。ダグラスさんが処方されていた薬のひとつ、クロナゼパム(リボトリール)のような癲癇(てんかん)治療に使われるベンゾジアゼピンの場合、現在、更に長い90日の処方日数が認められている。
一方、別府医師はまた、日本における医学教育を改善することが、これらの薬への中毒を予防するためには最も重要であると考えこう述べる。
「我々は、開業医や勤務医を再教育する必要があります。医薬品情報誌や専門誌を使って、彼らの薬や薬物療法に関する知識を向上させなければいけません」
更に、政府が製薬業界から強い影響を受け、薬の輸出を増加させることで国が儲かると政府は考えているとも別府医師は指摘する。
「人々に薬のリスクについて多く知らせることは、製薬企業にとって都合の悪いことです。それよりも、日本の製薬企業をより強くすることに関心が向けられているのです」
ページトップに戻る
(ベンゾジアゼピン中毒に関する情報)
ベンゾジアゼピン中毒に関する情報と薬から安全に離脱する方法については、アシュトン教授のウェブサイトで読むことが出来ます。
www.benzo.org.uk/manual/index.htm
コメントや取り上げて欲しい情報があればこちらからご連絡ください。community@japantimes.co.jp
ページトップに戻る
(∗1)
ここは原告第1陳述書、項目4の3 にある「症状が少し落ち着いた」という一節から引用されているが、新聞記事では“Douglas experienced a noticeable improvement in his condition(ダグラスさんは状態が著しく改善し)”と書かれている。実際は少し落ち着いただけで、“著しく”改善した訳ではない。
(∗2)
ここは原告第1陳述書、項目4の7のア にある「私の調子はどんどん悪化していきました」という一節から引用されているが、新聞記事では、“dizziness was markedly worse(目眩は顕著に悪化していた)”と書かれている。しかし、目眩の悪化は“顕著”ではなかった。
(∗3)
※3 ここは原告第1陳述書、項目4の7のア から引用されているが、その陳述書では、パニック発作のみについて言及されている。しかし、新聞記事では、多くの症状が残存しているかのように書かれている。正しくは、まず、「今でも残存している」とは、記事掲載日(2012年3月13日)の時点のことではなく、陳述書が提出された2008年1月時点のことであり、そして、その残存している症状とは、パニック発作だけである。
(∗4)
ここは原告第1陳述書、項目6の3 から引用されている。その陳述書では、主に復職が許可された2002~2003年時点のことについて言及されているが、新聞記事では、それからおよそ10年間も経過した記事掲載日(2012年3月13日)にも多くの症状が残存しているかのように書かれている。これは事実ではない。(詳しくは、回復について書かれたジャドスン医師による第3報告書、項目3.1 を参照して下さい。)
(∗5)
国連の一機関である、国際麻薬統制委員会による 2010年の報告書 によると、日本におけるベンゾジアゼピン系“抗不安薬(anxiolytic)”の平均消費量は、欧州各国の多くよりも少ないものの、アジアの中ではイラン に次いで最も多い(35頁、Figure 20参照)。一方、日本のベンゾジアゼピン系“催眠鎮静薬(sedative-hypnotic)”の平均消費量は、ベルギーを除くと世界のどの国よりも多い(39頁、Figure 26参照)。
ページトップに戻る
記事にあるように、私は、目眩発作で、歩くことも非常に困難になりました(ベンゾジアゼピン服用前)。複数の神経内科医が専門家として検証し、私に当初みられたこの疾患は前庭障害(前庭神経炎)であったことを示しています。私もそのように確信しています。私の知る限り、この疾患を発症する患者の多くは、深刻な平衡機能障害を呈しますが、このバランスの障害は、通常は、“代償作用”により時間をかけて徐々に自然治癒していきます。耳の神経から脳に送られる信号が、耳の神経の炎症により変化しても、代償的に、脳が脳自身を再調整することで治癒していくのです。
しかしながら、私のケースでは、神経系全体に作用する薬が多剤処方されたために、この自然治癒プロセスである“代償作用”が妨げられていたと確信しています。これにベンゾジアゼピン依存が加わったことが、私のバランス機能が元に戻るのにこれほど長期を要した原因であると私は考えています。実際、薬が身体から抜けきった後に初めて、私はバランスに関する障害から回復し始めたのです。最終的に、私は完全回復しましたが、それは薬が抜けきって初めて成し遂げられたことなのです。(了)
ページトップに戻る
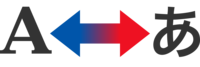
このサイトの主要言語は英語です。
その翻訳は私自身を含む複数の人によって手がけられました。
私の母国語は日本語ではありませんので何卒ご理解いただきたくお
What worked well?
What didn't work so well?

For the interest of the reader, in this site I have given feedback on what worked well in my case and what could have been done better.

Each one of us has a different experience of withdrawal.
The duration and degree of intensity can vary depending on the individual and there are many reasons for this.
It was difficult to get any relief from the ongoing symptoms

Unlike injuries where you may get some relief from adjusting your posture etc, with drug dependency in my case, the pain was both mental and physical and ran 24/7 regardless…
Throughout this entire ordeal, I came to realize the importance of “Balance”.

As pressing as the court deadlines were and as demanding as the case was, without maintaining a balance in life including rest, recreation, work, socializing, diet, sleep etc. it would have been impossible to sustain.
However, it was always a razor edge fine line between making progress and maintaining health and balance.
Subsequently, it took a lot of skill and adapting.

- 当方の重要証人である医長(診断医)は、裁判での証人尋問を2回拒まれています。1回目は東京地方裁判所で、2回目は東京高等裁判所においてです。
- 第1審決裁後の反証提出期限を過ぎてから、地方裁判所の裁判官は、被告側の有利になる問題を提出し、当方には反証提出の機会すら与えられなかった。
- 東京高等裁判所の裁判官は、中毒を引き起こすとみなされるベンゾジアゼピンの用量を決める際には、製薬会社が作成した添付文書に信用を置いて、提出された十二分なまでの証拠(疑う余地のない文献や専門家の意見など)を、あろうことか、無視した。
- 裁判では、被告医師が下した診断と、出された処方は整合性が取れないのだが、その矛盾は追及されることはなかった。
- 判決理由の記載の中身をみると、高等裁判所は、本件に適応されたDSM-IV-TR診断基準のうち、半分以上について検討していないことは明らかである。
- 訴訟中に裁判長の交代があった結果、本件について詳しい裁判長の代わりに、本訴訟の経過やベンゾジアゼピンについての基礎知識を全く持っていない新しい裁判長が途中で本訴訟を引き継ぐことになってしまった。
In my case, “confusion” appeared to be the main tactic of choice employed by the defense.

Enter the term “Autonomic Nervous Disorder” (The Perfect Smokescreen).
(Partial Reference: benzo.org.uk)
Journalists have regularly exposed the Benzodiazepine Scandal with stories of celebrity deaths attributed to benzo use as well as the blighted lives of ordinary people.
Benzodiazepines were, by all accounts, implicated in the deaths of:
- Elvis Presley
- Paula Yates
- Michael Jackson
- Heath Ledger
- Brittany Murphy
- Amy Winehouse
- DJ AM (a.k.a. Adam Goldstein)
- Anna Nicole Smith
- Margaux Hemingway
- Don Simpson
- David Foster Wallace
- Whitney Houston

How anti-anxiety meds are killing celebrities
It used to be that hard drugs were the cause of celebrity overdoses…Of the celebrities who have overdosed on drugs in the past five years, eight appear to have taken prescription medications — specifically, a mix involving easily accessible anti-anxiety medications known as benzodiazepines or “benzos.”
国際麻薬統制委員会2010年報告書によると、日本におけるベンゾジアゼピン系“抗不安薬(anxiolytic)”の平均消費量は、欧州各国の多くよりも少ないものの、アジアの中ではイランに次いで最も多い(35頁、Figure 20参照)。

一方、日本のベンゾジアゼピン系“催眠鎮静薬(sedative-hypnotic)”の平均消費量は、ベルギーを除くと世界のどの国よりも多い(39頁、Figure 26参照)。
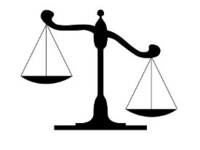
このセクションでは、私が闘った日本の裁判についてお話します。特にそこで現れた、明らかに不当な処置と思われる事例のかずかずを紹介します。これらの事例をわかりやすくお伝えするために、「東京高等裁判所の判決」と「中毒治療科の報告書」への参照箇所(リンク)がいくつか出てくるので是非ご参考ください。また、「中毒治療科報告書」は、一貫して、法的証拠およびDSM-IV-TRの依存症診断基準に基づいて書かれていることにもご留意ください。